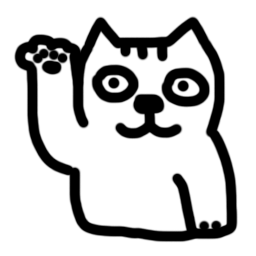招き猫の由来とは?
招き猫の由来にはいくつかの説があります。
今戸焼(いまどやき)説
今戸焼という陶器の職人が、貧しいながらも「人々に幸せを」と願って猫の土人形を作ったのが始まりとされます。浅草・今戸神社には「招き猫発祥の地」の碑もあります。
豪徳寺説
彦根藩主である井伊直孝が鷹狩りの帰りに寺の前を通った際、寺の飼い猫に手招きされて中に入ると、直後に雷雨が降りました。これを「猫に救われた」と喜び、寺を再興・寄進したことから「招き猫」のルーツになったと伝わっています。今も豪徳寺には大量の招き猫が奉納されていて有名です。
自性院説
室町時代の戦国武将で、江戸城を築城したことでも有名な太田道灌が鷹狩りの帰りに猫に手招きされて寺に入ったところ、雨に遭わずに助かりました。この寺も「招き猫発祥の地」を自称しています。
今戸焼の土人形説と豪徳寺の猫に救われた説が特に有名です。
招き猫は中国や台湾が由来と誤解していた人もいるかもしれませんが、上記を見ていただければ分かる通り、発祥は江戸時代の日本です。